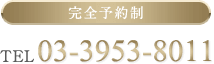歯髄温存治療について

通常、染みる程度の虫歯であれば、神経を除去することなく治療を終えることが出来ますが、虫歯が歯の歯髄(神経)まで達すると、神経を除去する「根管治療」が行われます。このような、根管部まで虫歯が進行してしまっている場合でも、歯髄を除去せずに残す治療が「歯髄温存療法」です。
歯髄温存治療では歯の神経を残しつつ、根管内の虫歯菌を清掃・消毒し封鎖材を詰めることで、神経を保護しながらも歯を治療することが可能となります。
神経を残すことで歯の寿命を延ばすことができ、将来的に歯を失わずに済むケースがあります。歯の状態や症状によっては、根管治療が必要な場合もありますが、他院で「神経を除去する必要がある」と診断された方でも、すぐに諦めることはせずに、一度当院へご相談ください。
神経を温存することの重要性

歯髄温存治療において神経を除去せずに残すことは、歯の寿命や形態、機能を維持するためにとても重要です。
神経を残すことで歯の自然治癒力が残され、歯の寿命を延ばすことができ、将来の抜歯のリスクを大きく低減することができます。歯を失うことは、食べ物の咀嚼や話し方、見た目などに影響を与えるため、極力歯を残すことが望ましいのです。
また、神経を除去した歯は、冷たいものや熱いものなどの刺激に対して感覚を持たなくなりますが、神経を残した歯は、感覚を維持することができます。他にも、神経を除去した歯は、時間が経つにつれて黄ばんだり、変色したりすることがあります。
神経を極力残すために必要なこと
マイクロスコープ拡大下の精密治療

マイクロスコープ拡大下の精密治療は、より正確かつ緻密な治療が求められる歯髄温存療法にとって、欠かすことの出来ない技術の一つです。
マイクロスコープは高倍率のレンズを備えており、肉眼では見えないような微細な部位を拡大して観察することができます。
特に歯髄温存療法では、細かな器具を使って根管内の感染している部分のみをしっかりと見極めて菌を除去する必要があり、適切な治療が行われない場合、再発するリスクが高くなるためです。
MTAセメントによる歯髄の保護
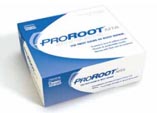
MTAセメントは、「Mineral Trioxide Aggregate Cement」の略称です。
虫歯の治療において感染歯質の除去を取り除いて行く際に、虫歯が神経まで達している場合、通常は神経を除去する「抜髄」という処置になりますが、露髄している部分の大きさによっては、露髄部分にMTAセメントを充填して神経を温存出来ることがあります。
全てのケースに適応出来るわけではありませんが、神経を取りたくないと思っている方には適した術式だと思います。別途、補綴(被せ物や詰め物)の費用はかかります。
MTAセメントは封鎖性殺菌性に優れているセメントで、身体との親和性も高いのが特徴です。セメントの成分が水分と反応して水酸化カルシウムが生成されて強アルカリ性になり、抗菌性が高くなります。通常の歯髄保護で用いられる水酸化カルシウムの製剤は硬化しないので辺縁封鎖性がイマイチですが、MTAセメントは完全硬化するので封鎖性が上がることで感染リスクが下がり、歯髄を温存出来る可能性が格段に上がります。
また、根の一部に穴が開いているケースでも、MTAセメントで穴を封鎖して歯の保存が出来る可能性が上がります。
MTAセメントは高価な材料であるため、自由診療になります。
歯髄温存治療Q&A
- Q:マイクロスコープがない歯科医院では、歯髄温存治療は受けられないのでしょうか?
- Q:MTAセメントは歯に塗布してから、どのくらいの時間で硬化するのでしょうか?
- Q:MTAセメントを使用した場合、再根管治療は難しいのでしょうか?
- Q:MTAセメントを取り扱っている歯科医院が少ないのは、なぜですか?
- Q:金属アレルギーがある場合、MTAセメントは使用できないでしょうか?
- Q:MTAセメントを適用できないのは、どのような状態の歯なのでしょうか?
- Q:痛みがある歯や、一度治療を受けている歯はMTAセメントは使用できないでしょうか?
- Q:MTAセメントとドックベストセメントは、どのような違いがあるのでしょうか?
- Q:他院で、神経を完全に除去したあとに、MTAセメントで埋めることを勧められましたが、神経を除去した歯にMTAセメントを入れる意味はあるのでしょうか?
- Q:他院で既に神経を抜く治療を開始しているのですが、やはり神経を残したいので、途中からMTAセメントを取り扱っている医院に相談しても、治療は受けてもらえないものでしょうか?
- Q:MTAセメントによる歯髄温存治療は、失敗するケースもあるのでしょうか?
歯髄温存治療のまとめ
歯髄温存治療においては、まず歯髄の状態を正確に診断することが重要です。歯髄の状態を把握するためには、歯の痛みや腫れ、感染症状などの症状を観察するとともに、歯髄のレントゲンなどの画像診断を行うことが必要です。
また、正確な診断に併せて、歯髄を保存するための専門技術が求められます。できるだけ歯髄を残すように、精密な治療が必要なためです。当院では、確かな技術と専門知識を持って、患者さんの歯を健康に保つための「歯髄温存治療」に対応しております。